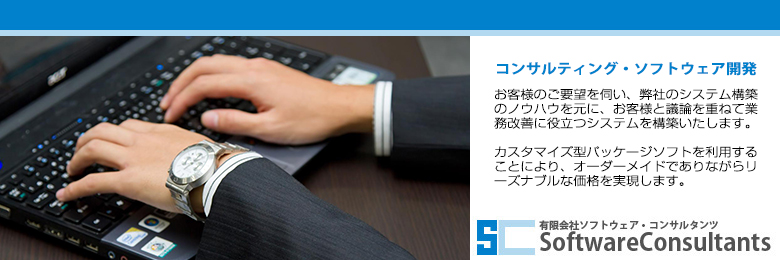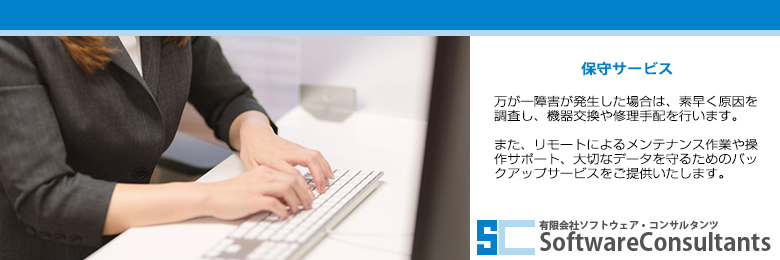御社ご自慢の商品をインターネットで販売してみませんか?
最近、色々な話題をふりまいている「IT関連企業」ですが・・・
まぁ、動かすお金の単位の大きいこと大きいこと。あれは私と同じ日本人なのか?な
どと驚きと羨望のまなざしでニュースを見ている今日このごろです。
みなさんは、もうインターネットで「お買い物」したことはありますか?
そう、いろいろなホームページへアクセスして商品を購入する、アレです。
マスコミなどでいろいろな被害が報じられていて、「インターネット」=「詐欺の
温床」のように感じているのかたも、まだ大分いらっしゃるようです。
しかし実際の商売でも同じですが、どこにでも悪い人はいます。人を騙すことを目
的とした人は、どのようなときでも「その機会」を狙っています。だからといってそ
ればかりを気にしていてもしかたがありません。そういう人の餌食にならないよう、
企業側もさまざまな防御策を講じますし、個人にもそれなりの意識改革が必要となる
のも、インターネット社会での新しいルールだと思います。
私達は商売柄10年以上前からインターネットに接する多くの機会がありました。
インターネットでのお買い物もたくさん利用しています。最初はパソコン用のソフト
ウェアやプロバイダ契約など、実際の形があるものではなく、「ライセンス」を中心
に購入していました。でもそのうち気がつけば、航空券、書籍、家電製品、生活用品
食品、貴金属、化粧品・・・随分いろいろ購入していました。いやいや自分でも驚き
です。
当初、インターネットで購入するときは「定価」で買うのが当たり前で、ただ単に
買い物に行くのが面倒臭いからネットショップを使う、という感覚だったのです。
「便利な分、高くてもしょうがない。その便利料は自分が払う」のというつもりでし
た。
しかしそのうちだんだん、「新商品の情報や出荷が早く」なり、最近では「ネット
ショップでの提示価格の方が安い」現象まで起きてきています。
そういえば、ネットショップには「建物」も「店員さん」も不要ですもんね。
企業もそういったコストを抑えて、それを直接、ネットショップ利用ユーザへ還元す
る、という傾向になってきたようです。
逆の言い方をすれば「店員さんからサービスを受けたい場合は、店舗へ来て陳列商
品を見ながら説明を受け、納得したら多少は高い価格で買う」時代になっていると、
言えるかもしれません。
そういったネットショップですが、2種類の店舗が存在するのはご存知ですか?
きちんとした線引きがあるわけでもありませんが、大まかに分類するとすれば、専門
店や直営店のような単一(もしくはJV)企業の経営する店舗と、テナントを集めた
ショッピングモールといわれるインターネット世界でのデパートに相当するものがあ
ります。
双方に特徴があり、どちらが主流というものでもありません。でも実社会のものと
比較するとそれぞれの販売方法のメリット・デメリットも見えてくるようですし、今
後も両者共存の道を歩むと思われます。
お客様が、商品をどこから購入するかを決める要因は複数あります。
商品が安い、納品までの期間が早い、扱い品目が豊富、質問をしたときに納得のいく
回答が得られる、などなど。どうせ「同じ商品を買うなら価格優先で」と考える人や
「希少価値の商品なら今すぐ入手できる方法で」と考える人などなど。
こういった購入者の心理はネット販売でも実社会と一緒ですね。
ただ、なんといっても手軽に「店舗も人員も用意しないで」たくさんの人に販売す
るチャンスを作ることが出来るというのは、ネット販売ならではの醍醐味ではないで
しょうか?
しかも、「いま売りたいものを、今日から販売できる」フットワークを持つことが
できるのです。
既存の販売ルートを気にせず、いままでに無い商品の販売でさえもOKとなると・・
そこで、いま弊社が行うキャンペーンのご案内です。
「御社ご自慢の商品をインターネットで販売してみませんか?」
今まではこういった場合、まずホームページを作りましょう!というのが常識でし
た。しかし自社ホームページを作成する場合、そのためにかかる初期コストや準備期
間はもちろん、さらに運用を開始してからの集客や宣伝活動のための手間隙は決して
少なくありません。
それならばをまず最初は簡単に商品の「手応え」をつかんでみたくなりますよね?
このような場合は先ほど述べたショッピングモールを利用してみるほうが、気軽に素
早くネット販売をスタートできます。
もちろんデパートへ出店するのですから、それなりの「テナント料」は必要になり
ますし、その中でのルールも存在します。しかしなんといってもインターネットの世
界でもデパートというところにはたくさんのお客様が歩き、ウィンドショッピングを
しています。商品をアピールできるチャンスは自社店舗とは比べ物になりません。
これにより、いままで全く取引をしていなかった相手にも、見てもらえるというの
は、デパート出店ならではなのです。
最初はこの方法で商品の手応えをつかみ、自社内での受注から出荷などの流れを確
認しながら、いよいよ「いける!」と思った段階で、次の自社ホームページ作成にす
すんでみるほうが安全で確実ですね。
インターネット販売というと、「お互いに顔の見えない取引」であることなどから
いかにも「危ない商売」の感じを受けますが、基本的には「通信販売」と同じです。
その通信販売も今でこそこれだけ普及してしまいましたが、当初は「?」という方
法だったようです。やはり商品は現物を見て買いたい・・・そういうものもあるのは
事実ですが、逆に写真だけで良いものや、店頭で見ただけではわからないものもあり
ます。通販はそういった分野から少しずつ普及していったようですね。
これからは、その通信販売がかなりネット販売へ移行するものと思われます。なぜ
ならネット販売では事前にカタログ配布をしなくてもよいので、初期コストが大幅に
少なくてすみます。(カタログ販売、及び作成関係の方、ゴメンなさい!)
新商品の陳列、売り切り商品の撤去、なども簡単ですし、特売のお客様へのご案内
も電子メールを使えば瞬時にお知らせできてしまいます。
こういったように、ネット販売を行うことにより、売り手と買い手の双方が大きな
メリットを与えられますので、今後この販売方法はますます浸透すると思われます。
そんななかで、いかに他社より「いいもの」を「安く」「早く」提供できるかが、
企業の生き残り条件となるのは、いままで以上に厳しく問われる環境が来るのです。
ショッピングモールへの出店は、皆様が手続きを行っても出来るものです。しかし
なかなか忙しいさなかには、新しい事業はやりにくいですよね?
そんな理由でみすみす販売するチャンスを見逃すのは、とても勿体ない・・・
そこでこのキャンペーンでは、皆様のショッピングモールへの出店手続きを全て弊
社へお任せいただけます。「何を、いくらで売りたい」だけご指示下さい。
経験豊富な弊社スタッフが、素早く出店・運営までサポートいたします。
いまこそ「御社ご自慢の商品をインターネットで販売してみませんか?」
なお、売れすぎの苦情はこちらまで↓
(井関)