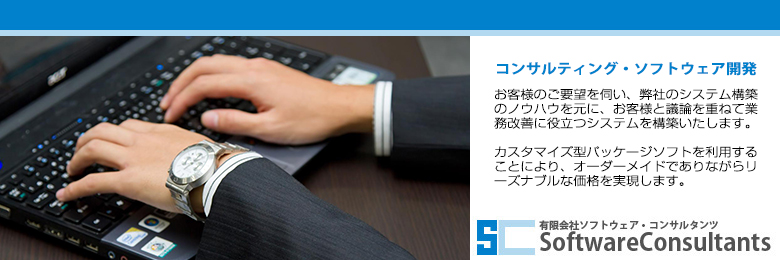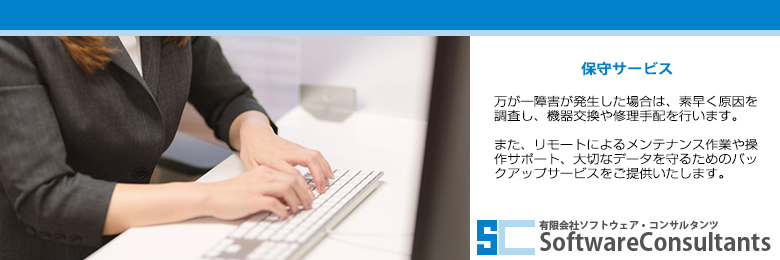マイクロソフトが自動更新を行うwindows update。IE7(IEとはInternetExplorer7.0
というバージョン。)もバージョンがIE6からIE7へ上がりアップデートより配布がス
タートし最近よく聞かれるのが「IE7って入れた方がいいんですか?」という質問です。
そこで今回はIE7へすることへのメリットをご説明したいと思います。
現行バージョンである「Internet Explorer 6」(IE6)はWindows XPのリリースに合わ
せて開発されていたため、正式公開からすでに4年以上が経ちますが、基本的な機能
はほとんど変わることがありませんでした。
しかし、この4年の間にインターネットの環境は大きく変わりウェブブラウザーに
ついては、米Mozilla Foundationの「FireFox」やノルウェーOpera Software ASA社
の「Opera」など、タブ切り替え等新しいインタフェースを持ったものが、一般でも
使われ始めています。マイクロソフトでは、次世代のOS「Windows Vista」のリリー
スに合わせて、IE自体のメジャーアップグレードを行なうことにしたのです。IE7の
テーマは3つ。
ユーザーエクスペリエンスの向上
IE7ではユーザーインターフェースが一新され、インターネットの最新テクノロジー
となっている“RSS(RDF Site Summary)”などへの対応が図られています。
高いセキュリティー機能
ここ数年、IEのセキュリティーホールが大きな問題となっているため、マイクロソフ
トではIEのコードを根本的に見直して、セキュリティーを大幅に高めています。
さらに、フィッシング詐欺やマルウェア(悪意あるソフトウェア)からの保護機能など
により、インターネット上の悪意のあるアクセスからユーザーを保護します。
プラットフォームと管理性の強化
IE7では、IE6で一部不整合な部分があった“CSS(Cascading Style Sheets)”の対応
について、“CSS 2.1”をサポートするとしています。これ以外にも、ウェブアプリ
ケーションを実現する最新のインターネットテクノロジーのひとつ“AJAX”のサポー
トやサーチ機能の強化などが行なわれています。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━………‥‥
┃ ┃セキュリティの強化
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━………‥‥
マルウェア対策
“Malware(マルウェア)”とは、システムに対してなんらかのトラブルを引き起こす
ことを目的にしたソフトウェアのことです。IE6はセキュリティー上の問題から、マ
ルウェアの侵入ルートとして利用されることが多かったため、IE7ではマルウェアの
侵入を防げるように設計されています。
クロスドメインスクリプト攻撃の抑止
クロスドメインスクリプト攻撃例を挙げると、ユーザーが悪意あるウェブページに
アクセスしたときに、正しいウェブサイト(例えば銀行のウェブサイト)の新規ウィン
ドウを開いてユーザーを騙し、IDやパスワードを入力させます。しかし実際にはハッ
カーのウェブサイトを経由しているため、銀行口座にアクセスするためのIDとパスワ
ードが盗み取られてしまいます。そこでIE7では、各スクリプトの生成元となるドメ
イン名を把握して、スクリプトの動作を同一ドメインに限定するようにしています。
したがって、ハッカーのウェブサイトで生成されたスクリプトでは、銀行のウェブサ
イトを直接利用できなくなり、悪意のあるウェブサイトが正しいウェブサイトのよう
に振る舞い、IDやパスワードを盗み取るのを防いでいます。
フィッシング(Phishing)対策
ここ近年インターネット上で大きな問題になっているのが“フィッシング詐欺”
代表的な例としてはクレジットカード会社や銀行のオンラインバンキングの偽サイト
を作って、ユーザーをメールなどで誘導し、IDとパスワードを盗みます。盗んだIDを
使い、被害者の口座から金を盗んだり、クレジットカードの偽造を行ない損害を負わ
せます。IE7では、フィッシング・フィルター (Phishing Filter)が搭載されていま
す。この機能ではURLを偽装しているサイトリストを、Microsoftが1時間に数回とい
う頻度でアップデートし、このリストを参照することで、ユーザーが偽サイトにアク
セスする前に警告を発します。これによりユーザーがフィッシング詐欺の引っかかる
ことを防ぐのです。
ウェブブラウザーに残る個人情報の削除手段の改善
IE7では、ユーザーがウェブブラウザー上でアクセスしたウェブサイト履歴や、入
力したIDやパスワードの情報を簡単に消去できるようになりました。インターネット
カフェや図書館など共用のパソコンを使うと、ユーザーが見たサイトや、サイトにア
クセスするときに使ったパスワードが共用パソコン上に保存されてしまいます。
IE7では、ユーザーが行なった作業(IE7のキャッシュ、パスワード、クッキー、フ
ォームデータ、閲覧履歴)などを簡単に消去できるようになりました。IE6でも消去は
できましたが、さまざまなダイアログにデータを消去するボタンが分散していました
そのため必要な作業手順を知らない一般ユーザーにとっては、自分が行なった作業の
痕跡すべてを消去する事は容易ではありませんでした。それをIE7では、まとめて消
去できるように1つのダイアログに集約されています。
ActiveXコントロールの管理の改善
“悪質なプログラムをインストールする”として問題になっていた“ActiveXコント
ロール”ですが、Windows XP SP2以上では“アドオンの可能”機能が用意され、イン
ストールされたActiveXコントロールを1つ1つ選んで、動作させるかどうか(有効/無
効)を設定可能となりました。これにより、問題がありそうなActiveXコントロールだ
けを無効にしたり、トラブルがあったときにはすべてのActiveXコントロールを無効
にすることが可能です。IE7では、必要のないActiveXコントロールを選んで、削除す
る機能も用意されています。
プラットフォームと管理性の強化
IE7ではインターネットの最新テクノロジーに対応するため、いくつもの機能が強
化されています。特にIE6で不評だった“CSS(Cascading Style Sheets)”の不整合を
修正し、”CSS 2.1”の準拠を最優先にしています。これによりIE6では“div”タブ
の処理が変更され、配置とレイアウトに関するバグ(※1)が修正されています。CSS2.
1のサポートを強化することで、ウェブページの表示をデザイナーの意図どおりに行
なうことができるようになりました。
AJAXサポートの改善
インターネットの最新テクノロジーとして注目を浴びているのが“AJAX(エージャ
ックス)”AJAXは “Asynchronous JavaScript+XML”という既存のテクノロジーを使
いながら、インタラクティブ性のあるウェブページを作成する技術です。例えば、プ
ラグインを使用せずにインタラクティブな地図サービスを提供している“Google Map
”や“MSN Virtual Earth” などは、AJAXによって構築されています。IE6では、AJA
Xが使用するXMLHTTPリクエストを、ActiveXコントロールによって処理していました。
しかしIE7はXMLHTTPリクエストをネイティブでサポートするようになり、互換性やセ
キュリティーの向上が図られています。
OSがRSSのプラットフォームに
RSS機能はOSのプラットフォームの一部 (Windows RSS Platform)としてサポートさ
れるようになりました。これによりVistaやXP SP2では、RSSの各種機能を Windows A
PI経由で、ほかのアプリケーションからも利用できるようになります。このRSS用API
では、RSSフィードのダウンロード、保存、アクセスなどがサポートされています。
マイクロソフトでは、既存のRSSを機能拡張した“Simple List Extension 1.0”仕様
をRSSコミュニティーに対して提案しており、IE7ではこの仕様が先取りでサポートさ
れています。この仕様を利用することで、ユーザーや開発者は情報のコンテンツリス
トのフィルター(絞り込み)やソート(分類/並べ換え)やピボット(表示切り替え)など
が簡単に行なえるようになります。またこれ以外にも、米Amazon.com社の子会社であ
る米A9.com社とマイクロソフトが共同で規格を策定した“OpenSearch”もサポートさ
れています。OpenSerachを利用すると、検索結果はXMLフォーマットで出力されます。
現在はHTMLで単にウェブページとして表示している検索結果を、XMLデータとしてさ
まざまなアプリケーションで利用できるようになります。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━………‥‥
┃ ┃操作性の変更点
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━………‥‥
ユーザーエクスペリエンスの向上・ユーザーインターフェースの変更
IE7をインストールしてまず気が付くのが、ユーザーインタフェース(UI)の変更で
す。IE6と比べると、ツールバーやエクスプローラーバーなどが非常にシンプルになっ
ています。ボタン類もシンプルになっていますから、ツールバーが何段も並ぶことも
ありません。FireFoxなど、競合となるウェブブラウザーと似たつくりとなっていま
す。
タブブラウザーのサポート
IE7を使ってみて最も大きく変わっているのが、タブブラウザー機能です。IE6でも
マイクロソフトが配布する“MSN Desktop Search”プログラムをインストールすると
IE6にタブブラウザーの機能を追加できます。しかしIE7では、最初からタブブラウザ
ーとして設計されている点が大きく異なります。タブブラウザーの表示の仕方も、単
にタブで表示を切り替える一般的な方式に加えて、現在アクセスしているページをす
べて縮小表示するという方式が用意されました。後者なら、タブブラウザーで数多く
のページにアクセスしても、どのタブがどのページかわからなくなるといったことも
なく、一覧画面を見れば目的のページが一目で判ります。タブをグルーピングするこ
ともでき、これにより、数多くのウェブページにアクセスしていても、分かりやすく
整理できます。さらにタブのグルーピングを保存しておき、IE7が起動するときに自
動的にウェブページにアクセスするように設定すると、起動してすぐにいつも見るペ
ージを表示できます。
ウェブページの拡大/縮小表示
ウェブページの表示に際して、拡大/縮小表示がサポートされました。この機能を
利用すれば、シニアのユーザーでも複雑なツールを使うことなく、ウェブページを見
やすく拡大できます。一方縮小を使えば、スクロールバーを使って表示しなければな
らない大きなウェブページの全体を見ることも可能です。
RSSフィードのサポート
IE7の大きな特徴のひとつといえるのが、RSSフィードへの対応があげられます。最
近では多くのウェブサイトで、記事の更新通知などにRSSを利用しています。IE7がRS
Sに対応したことで、RSSを利用して、どのウェブページにアップデートがあったのか
を簡単に知ることもできます。RSSのサブスクリプションを登録することも、ボタン
ひとつで行なえます。
Favorites Centerボタン
IE7ではLinkを登録する“Favorites”(お気に入り)に加えて、新たに“Favorites
Center”というボタンが用意されました。ここでは登録したお気に入りへのリンクだ
けでなく、“RSS Feeds”(RSSフィードの登録)や“History”(履歴)などに簡単にア
クセスすることが可能です。これらの要素が1ヵ所に統合されているので、非常に使
いやすくなりました。
標準で検索ボックスを用意
IE6では、標準ではツールバーに検索ボックスは存在しませんでした。一方IE7では
ツールバーに検索ボックスが用意されました。新設の検索ボックスでは、デフォルト
の“MSN Search”だけでなく、Yahoo!やGoogleなどの検索エンジンも登録することが
できます。これにより、使い慣れた検索エンジンを手軽に利用できます。各検索エン
ジン企業が個別にリリースしているツールバーソフトをインストールしなくてもいい
ため、ツールバー表示部分がごちゃごちゃしないのも利点と言えます。
ClearTypeフォントのサポート
IE7ではウェブページの表示に使うテキストフォントに、“ClearTypeフォント”が
利用できます。液晶ディスプレーでの視認性向上を重視したフォントのため、液晶デ
ィスプレーでのテキスト表示が見やすくなっています。
印刷機能の強化
もうひとつIE7での重要な機能は、印刷機能の強化です。IE6ではブラウザーに表示
されている画面を印刷しても、見た目どおりの出力結果にならないことが多かったと
思います。例えばウェブページの画面が大きいと、ページが2枚に分かれしまったり
してしまいます。それがIE7では、きちんと1枚の用紙サイズに収まるように、自動調
整する機能を持っています。これにより、ユーザーの見た目に近いイメージで印刷を
行なえるようになりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━………‥‥
私はIE6の操作に慣れてしまっているのでまだIE7へはしていませんでしたが、セキュ
リティの面を考えるとあげた方がいいのかもしれないと考えさせられました。
「絶対IE7にしなさい」とは一概には言えないのですが、個人的にはもう少し様子を見
てからIE7にあげたいと思います。
※対応OSはWindows XPとWindows Vistaになります。Windows XPはSP2以降となるので
IE7を使うにはSP2にアップデートしておく必要があります。また正規版のWindows OS
であるとの確認(Windows Genuine Advantage)がなされていないと、IE7はインストー
ルできないようになっています。
(ai)