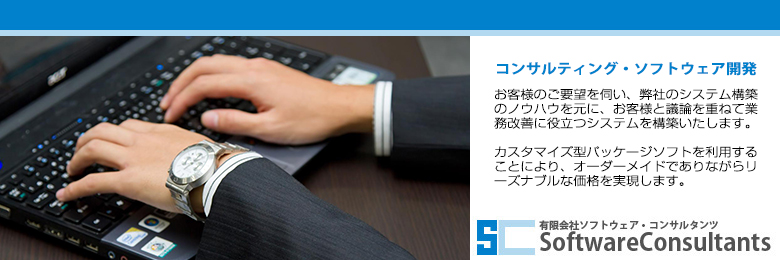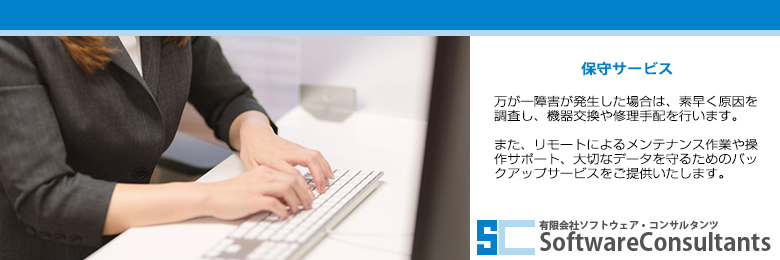皆様こんにちは。〝Windows Vista〟の次期主力OSとなる〝Windows 7〟のベータ
版が早くも公開され、2007年1月に出荷された〝Windows Vista〟はあと1年程度で主
力OSから退く可能性が高くなってきました。いい面も数多くある〝Windows Vista〟
ですが、企業での利用はなかなか進んでいないのが現状のようです。私の場合も
〝Windows XP〟〝Windows Vista〟の両OSが使える環境にはなっていますが〝Windows
XP〟を使用することの方が多いです。
今後、パソコン導入時のOSは〝Windows XP〟〝Windows Vista〟〝Windows 7〟と
いう選択肢になりそうです。〝Windows 7〟はまだ発売になっていないので実際にパ
ソコンにインストールすることはできませんが、現時点で〝Windows7〟へのUpgrade
権利付きのVistaが販売されていますので、それを購入するということになります。
また〝Windows XP〟のサポート期間は2014年までですので、あと数年はXPもOSの選
択肢として残りそうです。『Windows XPの環境も今後そんなに長くは続かない』、
『Windows 7がもう少しで出るならばそれまで待とう』等とパソコンやシステム導入
のタイミングが掴みにくい状況です。その辺りを踏まえて少々前置きが長くなりまし
たが、今回はOSを含めてソフトウェアにはどのような購入方法があり、それぞれに
どのようなメリットデメリットがあるかをご紹介したいと思います。少々長くなり
ますが、御社にとって有益な情報ですので最後までお読みいただければ思います。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━………‥‥
┃1┃現時点でWindows 7についてわかっていること
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━………‥‥
最初に現時点で分かっている〝Windows 7〟について少しご紹介します。
■主な特徴
・デスクトップの改良
アイコンの拡大やアプリケーション固有のメニュー表示ができるように
タスクバーが改良されている。
・管理機能の強化
ネットワークや機器接続など、関連する作業のメニューの簡素化や統合など
で分かりやすくなっている。
・クラウド(インターネット上のサービス)との融合
インターネット上でのメールやファイル共有機能がある「Windows Live」の
利用を前提とした管理機能を搭載している。
・ネットブック対応
最近流行りの低価格ノートパソコンでもスムーズな動作ができるようにCPU
性能やメモリ容量を低減させたエディションが用意されている。
■Windows7のエディション
・Windows 7 Home Premium
一般消費者向けのエディションでWindows Vista Home Premiumと同じ位置
付けになります。
・Windows 7 Professional
企業向けのエディションでWindows Vista Businessとほぼ同じ位置付けと
なります。MicrosoftではVista Businessをこのエディションに移行するこ
とを推奨しています。
・Windows 7 Enterprise
ソフトウェア アシュアランス(詳しくはこの後に)を購入している企業向
けで、このエディションはパッケージ販売やプリインストールするOEM販売は
行われません。データの保護機能等のより高度な機能を備えています。
・Windows 7 Home Basic
新興市場向けのエディションで国内では発売されない予定です。
・Windows 7 Starter
同時に実行できるアプリケーションを3つまでに制限した低価格ノートパソ
コン向けのエディションになります。
・Windows 7 Ultimate
Windows 7 各エディションの機能が全て入ったエディション。
パワーユーザー向けのWindows Vista Ultimateと同じ位置付けの
エディションとなります。
一般的には家庭向けがHome Premiumで企業向けがProfessionalという選択に
なると思います。
■実質上メジャーバージョンアップでは無いようです(ここが一番重要です)
〝Windows 7〟は〝Windows 98〟から〝Windows XP〟、〝Windows XP〟から
〝Windows Vista〟のようにOSの基本構造ががらり変わるメジャーバージョン
アップでは無く、中核となるプログラムは〝Windows Vista〟の拡張版となって
いて、基本的に〝Windows Vista〟対応のシステムはそのまま〝Windows 7〟で
稼働します。ですからシステムの入替等は〝Windows 7〟の登場を意識する必要
はなく、〝Windows XP〟環境のシステムを稼働させている企業は〝Windows
Vista〟対応という形でアップグレードを行っていけば、〝Windows 7〟にも
スムーズに対応していけるということになります。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━………‥‥
┃2┃OSライセンスの購入方法
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━………‥‥
次にOSライセンスの購入方法とそれぞれのメリット、デメリットについてご説明
したいと思います。OSの取得方法は下記の3つの方法があります。
1.店頭で販売しているパッケージ版を購入する
●メリット
・欲しい時に店頭で1ライセンスから購入できます。
・一度購入したライセンスはパソコンが壊れた等の際に、別なパソコンに
移して利用することが可能です。
(同時に複数台にインストールして利用することはできません)
●デメリット
・取得価格は3つの方法の中で一番高くなります。
・OSのインストール作業が必要です。
2.パソコン本体を購入する際にOSがプリインストールされたモデルを購入する
●メリット
・パソコンとセットで購入するので取得価格が3つの方法の中で一番安く
なります。
・OSをインストールする手間が省けます。
●デメリット
・ライセンスはセット購入したパソコン本体と一体となるので、パソコン本体
を破棄した場合はライセンスも一緒に破棄したことになります。
パソコンを利用しなくなったからといって、そのライセンスを他のパソコン
に移して利用することはできません。これはOSだけではなくOfficeも同じ扱
いとなります。
3.ボリュームライセンスプログラムを利用して購入する
●メリット
・ライセンスを比較的安く購入できます。
・ライセンス数の範囲であればどのパソコンにインストールしても利用でき
ます。
・下位バージョンOSの利用が認められています。(Vista Businessを購入
した場合 XP Professional、2000 Professional、NT Workstation、98、95
として利用することが可能です。)
・SA(ソフトウェア アシュアランス)契約を別途結ぶことにより契約期間内
に新バージョンが出た場合は無償でそのバージョンを利用することができま
す。
●デメリット
・最低3ライセンス以上のまとまった購入が必要になります。
・OSのインストール作業が必要です。
現状では2の方法で取得している企業様がほとんどだと思いますが、今後はぜひ
3の方法も検討していただきたいと思います。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━………‥‥
┃3┃ボリュームライセンスプログラムとは
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━………‥‥
前項でボリュームライセンスプログラムという聞きなれない単語が出てきました
ので、もう少し詳細にご説明いたしますと、ボリュームライセンスプログラムとは、
製品にかかわらず3ライセンス以上から購入ができる割引プログラムです。
購入から2年間が割引プログラムの適用期間となり、その期間内であれば1ライセンス
から追加購入が可能です。割引プログラムの適用期間が終了した後も、取得したライ
センスは無期限で通常通り利用できます。
■購入可能なライセンス
・ライセンス ・・・ 特定のOSやソフトウェアの使用権
・ソフトウェア アシュアランス ・・・ 割引プログラム適用期間内に新バージ
ョンが発売された際にアップグレード
を保証するオプション
・ライセンス& ・・・ 上記二つのセット
ソフトウェアアシュアランス
つまり、今ボリュームライセンスプログラムのライセンス&ソフトウェア アシュ
アランスを利用して〝Windows Vista Business〟を購入すると、〝Windows XP〟
〝Windows Vista〟に加えて今後発売される〝Windows 7〟を使用することが可能にな
ります。
また、3ライセンス以上の購入というのは同じ製品を3ライセンス購入する必要はな
く、〝Windows Vista Business〟〝Office Standard 2007〟〝Windows Server CAL〟
とパソコン1台を増設する時に必要なライセンス3本でも良いということになります。
いかがでしたでしょうか。〝Windows 7〟の特徴とシステムバージョンアップ時期
に〝Windows 7〟の登場は影響しないということ、そしてソフトウェアのライセンス
取得方法をご紹介いたしました。
では今パソコンの入替や増設を行う場合にどのOSを選択すればよいかということで
すが、実際問題これはお客様の現状のシステムを今後どのように拡張、バージョンア
ップを行っていくかに大きく左右されます。とにかく〝Windows XP〟のサポート終了
ギリギリまで使い続けるということであれば〝Windows XP〟が動作する比較的低スペ
ックな機種と〝Windows XP〟を選択すれば良いということになります(御社のために
も弊社のためにもあまりお勧めはしません)。そうではなく将来のシステムバージョ
ンアップに徐々に備えていきたいということであれば、比較的高スペックな機種と
〝Windows Vista〟を選択するということになります。
もうひとつ今回ボリュームライセンスプログラムをご紹介した理由に弊社がお勧め
しているパソコンメーカーのヒューレット・パッカード社よりOSが入っていないモデ
ルのパソコンが発売されました。一昔前には各メーカーからOSなしモデルというのが
発売されていたのですが、最近のOSなしモデルは高価なモデルか一部ショップの自社
ブランド機、または自作するしかなく、あまりお勧めできる機種はございませんでし
た。今回ヒューレット・パッカード社よりOSなしモデルが発売されたのをきっかけに
ヒューレット・パッカード社のほぼ同スペックの機種でプリインストールモデルとOS
なしモデル+ボリュームライセンスでの簡単な価格シミュレーションをしてみたとこ
ろ、以下のような結果となりました。
プリインストールモデル OSなしモデル
OS : Vista Business ダウングレード なし
CPU : Core2Duo E7300 Core2Duo E7300
チップセット: Q33Express G45Express
メモリ : 2GB 2GB
HDD : 80GB 80GB
OD : 16xDVD-ROM 16xDVD-ROM
モニタ : 19型液晶 なし
オフィス : Word Excel Outlook PowerPoint なし
保証 : オンサイト1年、パーツ3年 オンサイト1年、パーツ3年
本体価格 : 約97,000円 約50,000円
別途モニタ : 不要 約17,000円
別途Vista : 不要 約20,000円
別途Office : 不要 約40,000円
別途CAL : 約6,000円 約4,000円
インストール: 不要 約10,000円
総合計 : 約103,000円 約141,000円
パソコンの新規購入や増設の場合はプリインストールモデルの方がかなりお得に感
じますが、これがパソコンの故障や老朽化による入れ替え時のことを考えたらどうで
しょうか?プリインストール機ですと本体と一緒にライセンスも破棄することになる
のでまた約97,000円の費用が発生しますが、ボリュームライセンスでライセンスを取
得している場合の費用はソフトウェア部分が不要になるので、77,000円となります。
すでに皆様の会社には液晶モニタが揃っていることと思いますので、液晶モニタを購
入しなくてよいのであれば約60,000円の費用となります。今後OSをWindowsにしない
ということであればメリットはありませんが、現状そうではないと思いますので特に
台数を多く保有している企業様は是非ボリュームライセンスでの購入方法も選択肢の
一つとして弊社営業担当にご相談いただけたらと思います。
(TETSUYA)